当教室が中心に据えている科目は、音楽を書いてゆくための書法練習、即ち音楽理論系(和声実施)レッスンです。
ここでは、和声学の入門及び初級(一和音場につき一音のバス課題・ソプラノ課題)から諸段階を経て、
やがては上級レベルの『芸大和声3巻』(「階梯導入を伴うバス課題」etc.)を実施してゆけるよう、段階に応じたレッスンを行っております。
Ⅰ-1 専門的理論系科目 「和声学 」
(プレ和声学(楽典基礎)〉、〈和声学〉(和声Ⅰ・和声Ⅱ・和声Ⅲ・和声アドヴァンス)
Ⅰ-1. 専門的理論系科目〈プレ和声学(楽典基礎)〉〈和声学〉
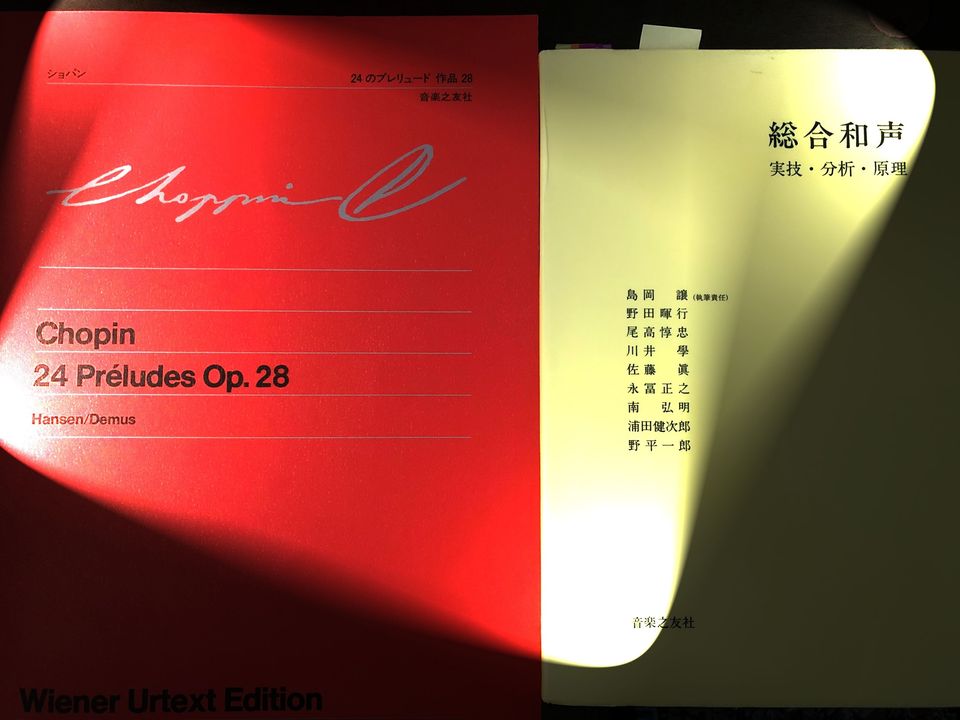
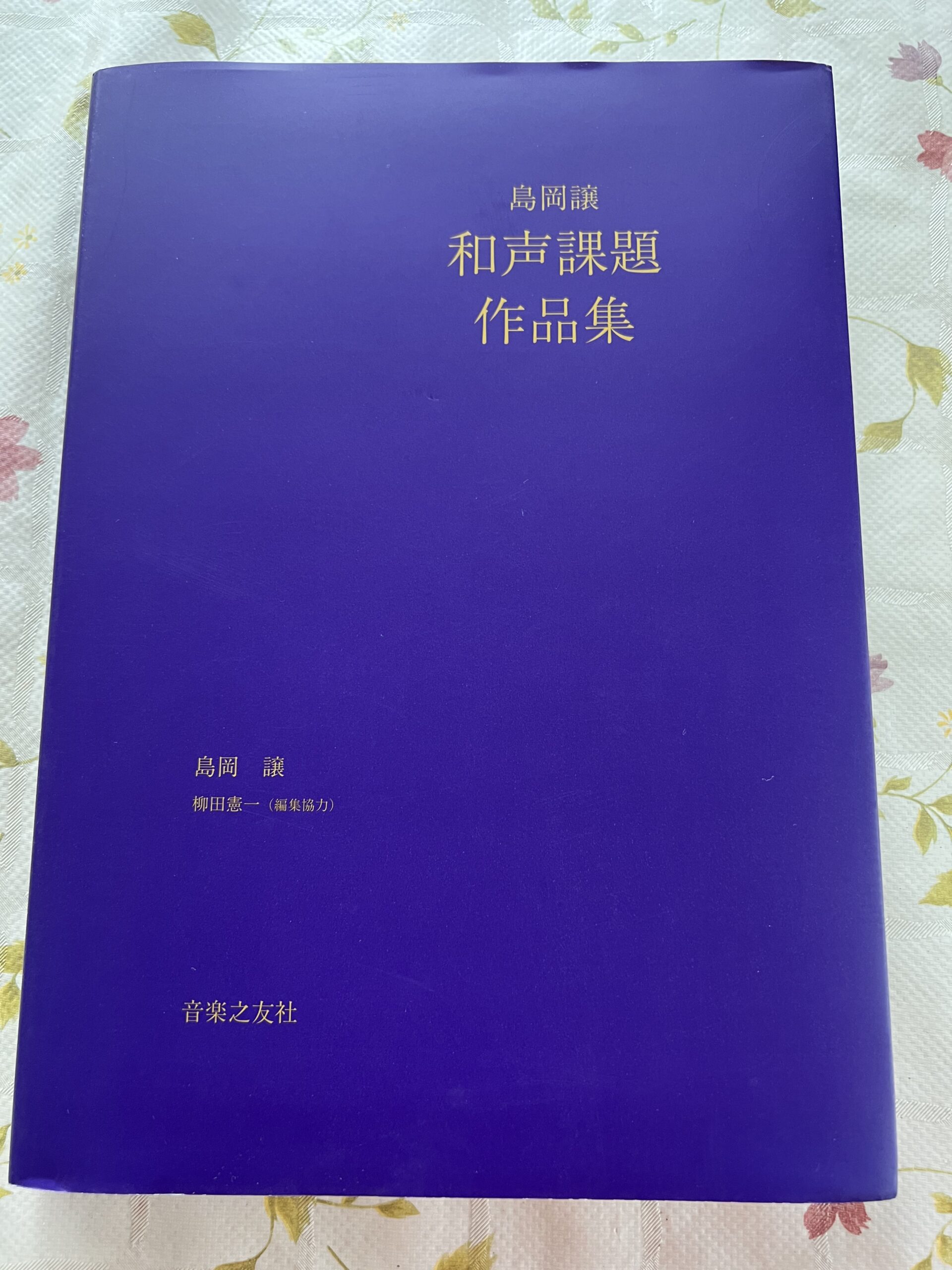
各レッスン概要
〈プレ和声(楽典)〉
初学者の方は先ずは『楽典』の基礎事項を抑えて、音楽上の文法を理解したのちに、必要に応じて『和声 入門ワーク』を用いて、四声体実施に慣れてゆきましょう。
〈和声学Ⅰ〉
楽典の基礎知識が既に身についている方は、バス課題の実施から入り、次にソプラノ課題の四声体実施を行います。始めは転調を含まない課題から入り、徐々に様々な転調・借用和音を含む和音連結を学習します。教科書は、島岡譲先生の『総合和声』を用いて、和声学習導入過程から第6章「さまざまなS和音」迄に相当する内容を実習するためのレッスンです。
〈和声学Ⅱ〉
「和声 Ⅱ」では転調や借用和音を含んだ和声課題(一音一場の課題)の実施を身につけられたかたの次のステップの学習となります。『総合和声』第7章「転位・修飾」、第8章「反復進行」及び第9章「偶成・保続」を含む和声課題を実習してゆきます。 (主に「自由ソプラノ課題」を中心に転位・修飾に慣れてゆく事が目的です。)
〈和声学Ⅲ〉
転位・修飾を伴った「自由ソプラノ課題」水準を学習された方の次のステップです。『和声 理論と実習Ⅲ』を用いて、バロック対位法様式に準拠した「『2個の主題の同時的提示』をもつバス課題」や、フーガ的な「階梯導入」によるバス課題などを実施してゆきます。ここで素材の展開の仕方や、「間接連続5度」、「間接連続8度」などの禁則も覚えてゆきます。
〈和声アドヴァンスコース 〉
『Challan 380和声課題集第9巻』や、『島岡譲 和声課題作品集』などを用いて四声体を実施します。
また、その他の課題を用いて大学入試和声過去問題などの「アルテルネ課題」の実習も行います。
Ⅰ-1. 専門的理論系科目〈プレ和声学(楽典基礎)〉・〈和声学〉
〈プレ和声学(楽典基礎)〉・〈和声学〉
プレ和声学(レベル:★~★★) |
音楽理論のビギナーコースです。先ずは楽典で基礎を養い、その後は『和声入門ワーク』を用いて、和声のしくみを学んでゆきます。 |
ワンレッスン/60分 ¥6,500- |
和声学Ⅰ (レベル:初級 ★★) |
作曲基礎として機能和声実施の四声体実施(リアリゼーション)を学びたい方から、西洋音楽の成り立ちの解き明かしとして、四声体実施を学びたい方のうち、 島岡譲先生の『総合和声』を用いて、和声学習導入過程から第6章「さまざまなS和音」迄に相当する内容を実習します。 |
ワンレッスン/60分 ¥7,000- |
和声学 Ⅱ(レベル:中級 ★★★) |
作曲基礎として機能和声実施を学びたい方から、西洋音楽の成り立ちの解き明かしとして、四声体実施(リアリゼーション)を学びたい方のうち、「一音一場」の和声リアリゼーションを或る程度習得された方の次のステップとして、「転位・修飾」の入った和声課題を実習するためのレッスンです。(「自由ソプラノ課題」を中心に) |
ワンレッスン/60分 ¥8,000- |
和声学 Ⅲ(レベル:上級 ★★★★) |
四声体実施(リアリゼーション)を学ぶ過程で、転位・修飾を伴った「自由ソプラノ課題」の続き、バロック対位法様式に準拠した「『2個の主題の同時的提示』をもつバス課題」や、フーガ的な「階梯導入」によるバス課題などを実施してゆきます。 |
ワンレッスン/60分 ¥9,000- |
和声アドヴァンスコース (レベル:アドヴァンス ★★★★★) |
『Challan 380和声課題集第9巻』や、島岡譲 和声課題作品集』などをを用いて四声体実習します。 また、その他の課題を用いて大学入試和声過去問題などの「アルテルネ課題」の実習も行います。 |
ワンレッスン/60分 ¥10,000- |
